| トップページ|信楽焼解説|信楽焼の見所|穴窯と登り窯 | |||||
| 信楽焼・解説 | |||||
|
about Shigaraki ware |
|||||
| 日本六古窯のひとつ・信楽焼
六古窯とは平安から鎌倉時代に始まったやきもの。瀬戸、常滑、丹波、備前、越前、信楽を指します。信楽焼は、それよりずっと以前、安土・桃山時代からすでにありました。 信楽焼の特徴 信楽焼のふるさとは、滋賀県の南、三重県との県境に近い滋賀県甲賀郡信楽町である。 信楽焼は、古来、無釉陶器(釉薬を掛けずに焼き締める陶器)を生産してきた。信楽の土は、質がよいことで名高い。ケイ石や長石が多く混じっているために、独特の肌の荒さがある。胎土に含まれる鉄分や焼成の具合で、発色は主に灰色から赤茶、稀な例では黒褐色とさまざまである。無釉陶器を生産する産地は信楽の他に も、伊賀、常滑、丹波などがあり少なくないが、信楽特有の土味は、登り窯、穴窯の薪窯焼成によって得られる温かみのある火色(緋色)の発色と自然釉によるビードロ釉と焦げの味わいに特色づけられ、素地肌の明るさにおいて際だっている。 その土味、つまり肌の風合いは、素朴さのなかに、日本人の風情を表現したものとして、室町・桃山時代以降、茶道の隆盛とともに「茶陶信楽」として千利休ら、いにしえの茶人にも愛され、珍重され、そして、 土と炎が織りなす芸術として“わびさび”の趣を今に伝えています。 |
|||||
| 信楽焼・見所 | |||||
|
Points of Shigaraki ware |
|||||
| 信楽焼の魅力 信楽焼の魅力は、窯のなかで炎の勢いにより器物にかかる、灰かぶりの現象により陶器に自然釉(ビードロ釉)が付着するという、窯変が生み出す独特の釉薬のかかり方にあるといわれています。 また、薪の灰に埋まる黒褐色になる部分を「焦げ」といい、古信楽にはしばしば見られる特徴的な窯変の現象が見られます 穴窯と呼ばれる素朴な窯で生産されたこれらは、一般に古信楽と呼ばれている。これら古信楽の持つ特徴の中でも、自然釉や焼き締めの不測の変化がやきものに与えた色合いや模様は、「景色」と呼ばれ、この場合は「味わい深い観察ポイント」といった意味として使われています。もちろん、人為的なものではなく、窯の炎の具合や様々な要素によって生じる偶然が生み出す窯変の有様を指しています。。「縄目」「火色」「焦げ」「灰被り」など、景色には数多くの種類と見分け方がある。 景色は、信楽焼を鑑賞する上で最も重要な見所と言えるでしょう。 以下、信楽焼の代表的な見所を含めさまざまな景色を紹介いたします。 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 景色は、窯焚き・窯詰め・土・造形など様々な条件の違いによって変わってきます。 気候(気温、気圧、湿度)なども大きな要素と考えられ、景色に影響を与えます。同じものは二つとできないと云われる所以でもあり、最大の醍醐味とも言えるでしょう。 |
|||||
| 穴窯と登り窯 | |||||
|
A anagama kiln and a climbing kiln |
|||||
| 穴窯 縄文式土器や弥生式土器は、野焼きという方法で焼かれていました。 地面を浅く掘り、小枝や薪を燃やし、その中で土器を焼くという方法です。しかしこのような野焼きでは、熱が逃げてしまい、温度も700度程度までしか上がりません。そこで熱が大気中を上昇するという性質を利用して、山の傾斜面に勾配を付けた穴を掘り、低い方から燃料を燃やし、蓋をして燃焼時の熱が逃げないような方法を考え出しました。これが穴窯の始まりだと考えられています。 窯としては歴史的にもっとも古く、原始的な構造を備えています。現代の様々な窯の祖型であり、火と土との戦いによって、力強く素朴な、神秘的なまでに美しい作品を現代まで時を超えて生み出している。 穴窯は合理性に欠け、経済性を無視する窯であり、だからこそ科学的な合理性と経済性が支配する現代社会の中で、穴窯の存在する意義が見直されていると考えられる。 |
|||||
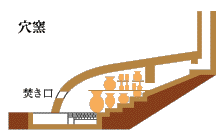 |
|||||
登り窯 穴窯に次いで、割竹式と言われる窯が出現します。これは半地上式の穴窯の房を連続させた形の窯で、数メートルごとに仕切りの区画壁を作り、その壁の下に炎の通る穴を設け、下の房から炎を溜めながら次の房に余熱を流す方式の窯で、この形式が登り窯の前進となります。登り窯は、一番最初の房が燃焼室で次の房からが焼成室(一の間、二の間・・・)となり燃焼室と焼成室が分かれている。また房を蒲鉾状にする事で炎の滞留時間が増え炎の状態は酸化傾向となり蓄熱にも一役買っている。これらの点が穴窯との大きな違いであり、両者の焼成にいろいろな違いをもたらすのである。 そして登り窯の開発による最大の恩恵は、直火で焼いていた穴窯に比べ不良品が少なくなり、また熱を合理的に蓄える(廃熱利用する)ことで燃料の節約となり、生産性が飛躍的に伸びた事にある。 |
|||||
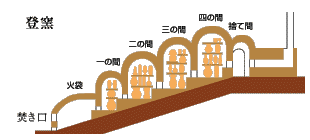 |
|||||
| トップページ|信楽焼解説|信楽焼の見所|穴窯と登り窯
|
|||||
| Copyrights(c)2006-Tetsuya Kowari All rights reserved | |||||
 緋色(火色)
緋色(火色) 焦げ
焦げ 灰かぶり
灰かぶり 自然釉
自然釉 ビードロ
ビードロ 長石
長石 抜け
抜け 窯変
窯変 貝目
貝目 窯しずく
窯しずく 目跡
目跡 ゴマ
ゴマ ひっつき
ひっつき 石はぜ
石はぜ 窯割れ
窯割れ